お金って何?
お金のはじまり:物々交換からお金へ
皆さんご存じの通り、昔はお金はありませんでした。
欲しいものがあったら、自分が持っているもので交換する「物々交換」という方法で手に入れていました。
例えば、「リンゴを持っている人が、パンが欲しい」と思ったとします。
パンを持っている人と出会って、「私のリンゴとあなたのパンを交換しませんか?」とお願いするわけですよね。
しかし、この物々交換には大きな問題がありました。
- 欲しいものと交換できるものがみつからない
相手が欲しいパンを持っていないかもしれない。 - 物の価値が分かりにくい
リンゴ1個とパン1個を交換するのは公平かな?なんて考えてしまう。リンゴの種類や大きさによっても価値は違うし、人によって好きなものも違うから、なかなか公平な交換が難しい。
お金が生まれる前の物々交換は、とても不便だったのです。
そこで、人類が生み出した便利な道具が「お金」です。最高の発明といってもいいでしょう。
お金があれば、直接欲しいものを買えますし、物の価値を測る基準にもなります。
例えば、リンゴ1個を100円、パン1個を80円と値段をつければ、誰でも簡単に価値を比較できます。
つまり、お金によって、こんなメリットが生まれました。
- 欲しいものをいつでも手に入れられる
お金さえあれば、欲しいものをいつでも買うことができるようになりました。 - 価値の比較が簡単になる
お金を使えば、ものの価値を数値で表すことができるので、公平な取引が可能になりました。 - 経済活動が活発になる
お金の登場によって、物々交換よりもはるかに大規模な経済活動が可能になりました。
また、お金には、モノを買うことや価値を測る以外にも、様々な役割・機能があります。
- 貯める: 将来のために、お金を貯めることができます。
- 貸す: お金を貸すことで、利息を得ることができます。
- 投資する: 株や不動産など、様々なものに投資して、お金を増やすことができます。
資産形成は、「貯める」→「投資する」のサイクルを回すことを意味しています。
(あ、もちろん、その前にお金を「稼ぐ」という行為が必要ですね。)
お金の種類:紙幣、硬貨、電子マネー、そして仮想通貨・暗号資産へ
お金には、私たちが普段使っている紙幣や硬貨の他に、様々な種類があります。
お金の種類についても見ていきましょう。
- 紙幣
紙幣は、国が発行するお金で、日本円の場合は日本銀行が発行しています。
1000円札、5000円札、1万円札などが一般的ですね。 - 硬貨
硬貨は、金属でできているお金です。
1円玉、5円玉、10円玉、50円玉、100円玉、500円玉などがあります。
紙幣と同様に、国が発行するお金です。 - 電子マネー
電子マネーは、ICカードやスマートフォンなどを使って、お金の代わりに決済できるサービスです。
SuicaやPASMOのようなICカード型や、PayPayやLINE Payのようなスマートフォンアプリ型など、様々な種類があります。国ではなく、民間事業者がサービスとして提供しています。
なぜ、こんなにたくさんのお金の種類があるのでしょうか?
それは、それぞれのお金が、異なる場面で使い分けられるようにするためです。
- 大きな金額の支払いには紙幣
例えば、家賃や家計費の支払いは、紙幣を使うことが多いでしょう。 - 小さな金額の支払いには硬貨
自動販売機や駐車場など、少額の支払いは、硬貨を使うことが多いでしょう。 - 手軽な支払いは電子マネー
コンビニやスーパーでの買い物など、手軽に支払いを済ませたい場合は、電子マネーが便利です。
このように、お金は時代の進化とともに変化してきているわけです。
昔は、貝殻や家畜などがお金の代替として使われていました。
その後、金属貨幣、紙幣、そして電子マネーへと、お金の形は大きく変わってきました。
そして今、国に依存しない通貨が登場しました。ビットコインに代表される仮想通貨・暗号資産です。
資産形成を考えていく上では、お金の意義や意味、なぜ登場したのか、を押さえておくことが大事です。
投資が投機(ギャンブル)にならないようにするためには、投資対象となる資産が将来どのような価値を生み出すのかを理解した上で、投資することが必要になるわけです。
(投資対象には株式投資や不動産投資、仮想通貨・暗号資産等、さまざまありますが、それぞれはまた別記事で紹介をしていきます。)
経済ってなんだろう?
経済活動:モノを作り、売る、買う
私たちが毎日使っているスマホや、美味しいお菓子、着ている服。これらのものは、どこから来たのでしょうか?
答えは簡単です。誰かが作って、売って、そしてあなたが買ったからです。
この一連の流れを「経済活動」と言います。
モノが生まれるまでをプロセスで見ていきましょう。
- 生産
まずは、モノを作ることから始まります。工場で車が作られたり、畑で野菜が育てられたりします。
このモノを作ることを「生産」と言います。 - 流通
生産されたモノは、お店に運ばれたり、インターネットで販売されたりします。
このモノを消費者のところに届けることを「流通」と言います。 - 消費
最後に、私たちがお店に行ってモノを買ったり、インターネットで注文したりします。
この買うことを「消費」と言います。
経済活動は、ただモノが作られ、売られるだけではなく、お金が循環することで成り立っています。
- お金の動き
あなたがお菓子を買うと、そのお金はお菓子を作った会社に入ります。
会社はそのお金を使って、新しいお菓子を作ったり、従業員に給料を支払ったりします。 - 経済の輪
このように、お金は生産者から消費者へ、そしてまた生産者へと、絶えず循環しています。
このお金の循環が、経済を活発にし、社会を豊かにします。
そして、このような経済活動は、私たちの生活と密接に結びついています。
- 新しいモノが生まれる
経済活動によって、新しいモノやサービスが生まれ、私たちの生活は豊かになります。 - 仕事が生まれる
モノを作る人、売る人、運ぶ人など、経済活動には様々な仕事が生まれ、人々は仕事を通じて生活を支えています。 - 社会の仕組みを支える
税金は、経済活動を通して集められ、道路や学校などの公共施設の整備に使われます。
経済活動は、モノが作られ、売られ、買われる一連の流れです。
この活動は、私たちが日々暮らす上で必要不可欠なものであり、社会全体を支える重要な役割を果たしています。
経済の輪:お金が循環する仕組み
今度はお金の動きに着目してみていきます。皆さんがお店で買った商品、そのお金はどこへ行くのでしょう?
そして、お店で受け取ったお金はどこから来たのでしょうか?
お金は、私たちの社会の中で絶えず循環しています。このお金の循環が、私たちの経済を動かす原動力です。
お金の循環は、とてもシンプルでありながら、複雑な仕組みでもあります。
お金の循環の基礎は以下の通りです。
- 生産
企業がモノやサービスを作り出します。この時、原材料や人件費などにお金を使います。 - 流通
生産されたモノやサービスは、お店やインターネットを通じて消費者へ届けられます。 - 消費
消費者は、欲しいモノやサービスをお金と交換します。 - 再び生産者へ
消費者が支払ったお金は、企業に戻り、再び生産に利用されます。
そして、経済の輪は、ただ単に繰り返されるものではありません。
様々な要因によって、その大きさは変化します。例えば以下のような要因です。
- 企業の投資
企業が新しい工場を建てたり、新しい製品を開発したりすると、経済活動が活発になり、お金の循環が加速します。 - 政府の役割
政府は、公共事業や税制を通じて経済に影響を与えます。
例えば、新しい道路を作ったり、税金を減らしたりすることで、経済活動を活性化させることができます。 - 海外との取引
輸出入を通じて、国と国との間でお金がやり取りされます。
お金は、私たちの社会の中で、生産、流通、消費という一連の流れの中で循環しています。
このお金の循環が、経済を活性化させ、私たちの生活を豊かにするわけです。
言い換えると、お金の循環が悪くなると、経済が不活性になります。
日本は長らくこの状況が続いていましたよね。
経済の主役:企業、消費者、政府
経済活動は、私たちの生活を支える上で欠かせないものです。
この経済活動において、重要な役割を果たしているのが、企業、消費者、そして政府という3つの主体です。
それぞれがどのような役割を担い、経済にどのような影響を与えているのか、詳しく見ていきましょう。
<企業:経済のエンジン>
企業は、商品やサービスを生産し、市場に供給することで、経済を活性化させる存在です。
- 技術革新
企業は、新しい技術や製品を開発することで、経済成長を牽引します。
例えば、スマートフォンやインターネットの普及は、企業の技術革新によって実現されました。 - 生産活動
企業は、原材料を仕入れ、労働力を雇用し、製品を製造します。
この生産活動を通じて、新たな価値を生み出します。 - 雇用創出
企業は、従業員を雇用することで、人々に仕事を提供します。
雇用が増えることで、国民所得が増加し、消費も活発になります。
<消費者:経済の原動力>
消費者は、企業が生産した商品やサービスを購入する存在です。
消費者の購買行動は、企業の生産活動に大きな影響を与えます。
- 需要の創出
消費者が商品やサービスを求めることで、企業は生産を増やしたり、新しい商品を開発したりする動機を得ます。 - 経済の循環
消費者が商品を購入すると、そのお金は企業に流れ込み、再び生産活動に利用されます。 - 市場の形成
消費者の多様なニーズに応えるために、企業は様々な商品やサービスを提供します。
消費者の好みやトレンドは、市場の形成に大きな影響を与えます。
<国・政府:経済の舵取り役>
政府は、経済全体の安定と発展のために、様々な政策を実施します。
- 経済政策
政府は、景気刺激策や金融政策など、経済状況に合わせて様々な政策を実施します。 - 規制
政府は、企業の不正行為を防ぎ、消費者を守るために、様々な規制を設けます。 - 公共サービスの提供
政府は、教育、医療、インフラ整備など、国民生活に必要な公共サービスを提供します。
<3者間の関係>
企業、消費者、政府は、それぞれが密接に関連し合いながら、経済を動かしています。
- 企業は、消費者のニーズに応えるために商品やサービスを提供し、政府の政策によって活動が規制されます。
- 消費者は、企業が提供する商品やサービスを購入し、政府が提供する公共サービスを利用します。
- 政府は、企業の活動を規制し、消費者を保護するとともに、経済全体を安定させるための政策を実施します。
経済活動は、企業、消費者、政府という3つの主体の相互作用によって成り立っています。
それぞれの役割を理解することは、経済の仕組みをより深く理解するために不可欠です。
資本主義ってどんな世界?
資本主義の考え方:自分でお金を増やせる
少し回りくどかったかもしれませんが、お金、経済、そしてその循環の基本が理解できたところで、資本主義とは何かについて概要を押さえていければと思います。
資本主義は経済成長と個人の自由の両立ができる社会システムです。
経済成長の面でみると、自由な競争が経済成長を促し、消費者のニーズに応える多様な商品やサービスが提供されます。その結果、人々の生活水準が向上するわけです。
(もちろん経済成長のために環境等が犠牲になってきた過去がありますから、すべてを称賛するわけにはいかないですけどね。)
個人の自由の面で見ると、個人が自由に経済活動を行い、その成果を享受できる社会システムのことです。
自分でお金を稼ぎ、それを元手にさらに大きなお金を稼ぐことができる社会と言えます。
努力次第で誰でも豊かになる可能性があるということです。
でも裏を返すと、その社会システムに乗れない場合は、低所得、失業や貧困などに繋がってしまうという負の側面もあるわけです。
資本主義において、自分でお金を増やすための方法は様々あります。
まず、どのような方法があるのかをきちんと理解していきましょう。
この理解が今後の資産形成を考える際の基礎になります。
- 労働
自分のスキルや能力を活かして働くことで、賃金を得ることができます。 - 投資
株式や不動産など、様々な資産に投資することで、資産を増やすことができます。 - 事業(起業)
新しいビジネスを立ち上げ、その収益を得ることができます。
「お金持ちには、お金が降ってくる」といった言葉を聞かれたことあると思いますが、
お金持ちはこのお金を増やす方法を知っているから、増えるのです。
加えて、元手となるお金の金額も大きいことから、さらに大きく増えるわけです。
例えば、10億円を保有していて、年利5%の投資ができれば、1年間に10億円×5%=5,000万円が増えるわけです。
こういった資本主義のメカニズムを当たり前のように親から教わり、受け継がれているわけです。
一方で、多くの日本人はどうでしょうか。
私自身もそうでしたが、高校または大学を卒業したら企業に就職する、企業で働いて給料を得る、そしてその企業に長く勤める、といったことが当たり前のように教えられています。今だにです。
でも実は資本主義は、上述の通り、労働者がいないと成り立たない側面があります。
労働者がいないと企業はサービスを提供できなくなるからです。
だから定年まで企業で働くように教えておいたほうが色々都合がよいわけです。
誰にとって都合がよいか?そうです、国や資産家です。
このブログの一番の問いはここにあります。
「あなたはこれからも労働者として時間を切り売りしいながら働き続けますか?」
それとも
「資本主義のメカニズムやルールを理解して、資産家側のほうになりますか?」
このブログを通じて学びながら、資産形成の道を一緒に歩んでいきましょう。

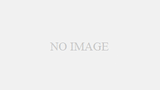
コメント