はじめに:なぜ今、インデックス投資が注目されているのか?
投資に興味はあるけど、何から始めたらいいかわからない…。
株はリスクが高いイメージがある…。そう思っている方もいるかもしれません。
確かに、個別株の売買は専門知識が必要で、リスクも伴います。
しかし、投資にはリスクを抑えながら長期的な資産形成を目指せる方法があります。
それが「インデックス投資」です。
この記事では、投資初心者の方でも安心して始められるインデックス投資の魅力と具体的な方法をご紹介します。
日本の経済状況と将来への不安
日本経済は長らく低成長が続いており、将来への不安は増すばかりです。
特に、老後資金の問題は深刻で、「老後2000万円問題」という言葉が広く知られるようになりました。
これは、年金だけに頼った生活では、老後資金が2000万円不足する可能性があるという試算に基づいています。
総務省の家計調査によると、高齢夫婦無職世帯の平均的な生活費は月約27万円となっています。
一方、平均的な年金受給額は約22万円です。
この差額を毎月貯蓄から取り崩していくと、老後30年間で約2000万円の不足が生じるという試算です。
物価の上昇、年金受給額の減少、医療費の増加などを考慮すると、この金額はさらに大きくなる可能性もあります。現役世代は、将来の生活を支えるために、預貯金だけでなく、積極的な資産形成を考える必要に迫られています。
(そういう状況もあって、NISA制度の整備等、国も躍起になっているわけです。老後を国の責任から個人の責任に徐々に転嫁していくわけです。)
資産形成の必要性
物価が継続的に上昇する現象をインフレーション(インフレ)といいます。
インフレが進行すると、同じ金額で買える物の量が減ってしまうため、お金の価値が目減りします。
例えば、今まで100円で買えていたパンが、インフレによって110円になったとすると、同じ100円ではパンを買えなくなります。
つまり、お金の価値が下がったということです。
預貯金だけでは、このインフレによってお金の価値が目減りしていくリスクがあります。
そのため、物価上昇に合わせて資産価値も増やしていく資産形成が必要となるのです。
上記で老後2,000万円が不足するという試算を記載しましたが、インフレが想定以上に加速すれば、もっと金額が必要になることになります。
銀行にお金を預けておけば安心、そう考えている方もいるかもしれません。
確かに預貯金は安全性の高い資産運用方法の一つですが、現在の超低金利環境下では、預けているお金はほとんど増えません。
むしろ、前述のインフレが進行すると、実質的な資産価値は目減りしていくことになります。
つまり、預貯金は「お金を守る」という役割は果たせても、「お金を増やす」という役割は十分に果たせないのです。
将来の生活水準を維持するためには、預貯金に加えて、積極的に資産を増やしていく方法を考える必要があります。
インデックス投資とは?基本を分かりやすく解説
インデックスとは?
インデックスとは、簡単に言うと「市場の平均点」のようなものです。
例えば、学校のテストでクラス全体の平均点を出すように、株式市場全体の平均的な動きを表すのがインデックスです。
日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)といった言葉をニュースなどで聞いたことがあるかもしれませんが、これらは日本の株式市場の代表的なインデックスです。
これらのインデックスを見ることで、市場全体が上がっているのか、下がっているのかを大まかに把握することができます。
もう少しかみ砕くと、インデックスとは、株式や債券などの市場全体の動向を示す指標や指数のことです。
具体的な例としては、以下のようなものがあります。
- 日経平均株価: 東京証券取引所プライム市場に上場している代表的な225銘柄の株価を基に算出される指数です。日本の株式市場全体の値動きを示す代表的な指標として広く知られています。
- TOPIX(東証株価指数): 東京証券取引所プライム市場に上場しているすべての銘柄の株価を基に算出される指数です。日経平均株価よりも幅広い銘柄の動きを反映しています。
- S&P500: アメリカの代表的な500銘柄の株価を基に算出される指数です。アメリカの株式市場全体の値動きを示す指標として広く利用されています。
インデックス投資の仕組み
個別株投資は、特定の企業の株式に投資する方法です。
例えば、トヨタ自動車の株を買う、ソニーの株を買うといったように、個別の企業を選んで投資します。
そのため、その企業の業績や株価の変動が、投資成果に直接影響します。
一方、インデックス投資は、特定の指数(例えば日経平均株価やTOPIX)に連動するように運用される投資方法です。
つまり、個別の企業ではなく、市場全体に投資するということです。
例えば、TOPIXに連動するインデックスファンドに投資すれば、東証一部に上場するすべての企業の株に分散投資しているのと同じ効果が得られます。
インデックス投資は、特定のインデックス(株価指数)の値動きに連動するように運用される投資方法のため、例えば、日経平均株価に連動するインデックスファンドに投資した場合、日経平均株価が上がればファンドの価格も上がり、日経平均株価が下がればファンドの価格も下がります。
つまり、市場全体の平均的な動きに投資するということです。
インデックス投資は、主に「インデックスファンド」と呼ばれる投資信託を通じて行われます。
インデックスファンドは、特定のインデックスを構成する銘柄を組み入れて運用されます。
例えば、TOPIX(東証株価指数)に連動するインデックスファンドであれば、TOPIXを構成するすべての銘柄、またはそれに近い銘柄を組み入れて運用されます。
これにより、ファンドの価格はTOPIXの値動きとほぼ同じように変動します。
投資信託とは?:インデックスファンドとアクティブファンドの違い
投資信託とは、多くの投資家から集めたお金を一つにまとめ、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに投資・運用する金融商品です。
投資家は、投資信託を購入することで、少額からでも分散投資を行うことができ、専門家による運用の恩恵を受けることができます。
投資信託には大きく分けて「インデックスファンド」と「アクティブファンド」の2種類があります。
繰り返しですが、インデックスファンドは、特定の指数(例えば日経平均株価やTOPIX、S&P500など)の値動きに連動するように運用される投資信託です。
つまり、市場全体の平均的な動きに投資をし、市場平均と同等のリターンを目指します。
一方で、アクティブファンドは、ファンドマネージャーが市場平均を上回る成績を目指して、個別の銘柄を選定したり、売買のタイミングを計ったりする運用方法です。
ファンドマネージャーの分析力や運用能力によって、市場平均を大きく上回るリターンを得られる可能性がありますが、逆に市場平均を下回る可能性もあります。
アクティブファンドは、銘柄選定や売買に手間がかかるため、運用コスト(信託報酬)がインデックスファンドに比べて高い傾向にあります。
投資初心者の方は、まずインデックスファンドから始めるのがおすすめです。
インデックスファンドは、比較的低コストで市場全体に分散投資できるため、リスクを抑えながら長期的な資産形成を目指すことができます。
ある程度投資経験を積んで、より高いリターンを狙いたいと考えるようになったら、アクティブファンドを検討してみるのも良いでしょう。
ただし、アクティブファンドは運用コストが高く、必ずしも市場平均を上回る成績を上げられるとは限らないことを理解しておく必要があります。
ちなみに私自身は、インデックスファンドのみで十分だと考えています。
長期的にはインデックスファンドが優秀
アクティブファンドよりもインデックスファンドが長期的に見て優秀であるという根拠となるデータは、数多くの調査や研究によって示されています。
S&P Dow Jones Indices社が定期的に公表している「SPIVA(S&P Indices Versus Active)スコア」は、アクティブファンドとベンチマーク指数(例えばS&P500など)のパフォーマンスを比較したデータです。このスコアは、長期的に見てアクティブファンドがベンチマーク指数を上回るのがいかに難しいかを示しています。
SPIVAの過去のデータを見ると、米国株式市場において、過去10年間でS&P500指数を上回ったアクティブファンドの割合は、わずか10〜20%程度にとどまっています。
つまり、ほとんどのアクティブファンドは、長期的に見て市場平均に負けているということです。
投資の神様として知られるウォーレン・バフェット氏は、自身の遺言で妻に「S&P500のインデックスファンドに投資するように」と指示していることを公言しています。
これは、長期的に見てインデックスファンドがアクティブファンドよりも優れたパフォーマンスを発揮する可能性が高いと考えているからです。
ETF(上場投資信託)とは?
投資信託を色々学んでいくと、ETFという言葉を見かけます。
ETF(Exchange Traded Fund)は、「上場投資信託」とも呼ばれ、株式市場で取引できる投資信託です。
通常の投資信託は、販売会社(証券会社や銀行など)を通じて購入・解約を行いますが、ETFは株式と同様に、証券取引所で売買することができます。
そのため、取引時間中はリアルタイムで価格が変動し、株式と同じように売買のタイミングを計ることができます。
投資信託とETFは同様の商品があるため、どちらに投資する方がよいかよくテーマに挙がります。
こちらを記載すると記事が長くなってしまうので別途書きたいと思います。
ここでは、ETFは、市場で売買できるということが理解できていればOKです。
インデックス投資のすすめ
インデックス投資のメリット
インデックス投資は分散投資を容易に行えるというメリットがあります。
指数を構成する多数の銘柄に自動的に分散投資されるため、個別企業の業績変動によるリスクを抑えることができます。
これは、個別株投資に比べてリスクを抑えながら安定的なリターンを狙うことができるということを意味します。
また、運用方法がシンプルで分かりやすいため、投資初心者でも安心して始めることができます。
市場全体の平均的な成長に連動することを目標としているため、複雑な分析や市場の動向を常にチェックする必要もありません。
また、その手軽さと低コストもメリットです。
特定の指数(例えば日経平均株価やTOPIX、S&P500など)に連動するように運用されるため、個別の銘柄選定を行う必要がありません。これは、投資初心者にとって大きな利点となります。
また、アクティブファンドのようにファンドマネージャーが積極的に運用を行う必要がないため、運用コスト(信託報酬)が比較的低い傾向にあります。
この低コストは、長期投資においては複利効果を最大限に活かす上で非常に重要です。
投資の原則は「長期」「分散」「低コスト」であるため、インデックスファンドはこの原則に合致した投資商品といえます。
インデックス投資のデメリット
一方で、インデックス投資にはデメリットも存在します。
一般的によく言われるのは、市場平均以上のリターンを期待できないということです。
インデックス投資は、あくまで市場平均に連動することを目標としているため、市場が大きく上昇したとしても、市場平均以上のリターンを得ることはできません、という考え方です。
”市場平均”という言葉を聞くと、あまり儲からないという印象を受けますよね。
実はこれが誤解で、インデックス商品は5%~20%ぐらいの利回りの商品が多くあります。
そのためリターンが低いというのは誤解・誤認にあたるケースが多く、クリティカルなデメリットにはならないと私は考えています(むしろ個別株よりもメリットが大きい)。
インデックス投資は、特定の指数に連動するように運用されるため、投資対象を選ぶ自由度が低いというデメリットもあります。
例えば、特定の業種やテーマに投資したい場合、適切なインデックスファンドが存在しない場合があります。
ただし、基本的なニーズを満たす商材は多く存在しますから、こちらもクリティカルなデメリットとはいえないでしょう。
インデックス投資は、長期的な視点で資産形成を行うことを目的としているため、短期的な値動きに惑わされずに長期保有することが重要です。
短期的な値動きに敏感に反応してしまうと、本来得られるはずのリターンを逃してしまう可能性があります。
例えば、2008年のリーマンショックや2020年のコロナショック時にはインデックスも暴落しました。
こういう時にも握力強く握り続けられるかが非常に重要です。
(なお、暴落時は株価が下がっているわけですから、本来は一番買いのチャンスなのです。
ですが多くの投資家は怖くなって売ってしまいます。逆の動きをしてしまうわけです。)
私が考える一番のデメリット(正確に言うとデメリットを引き起こしてしまう)はこの短期的な値動き時のマインドと動き方になります。暴落時にインデックス投資の意味・意義をきちんと理解し、冷静になり、むしろ余力資金を使って、買い進めることで、将来の上昇局面で大きな利益を得ることができます。

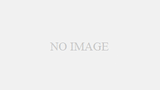
コメント