資産形成でなぜリスクとリターンが重要なのか?
「将来、お金に困らないで暮らしたい」、「老後も安心して過ごしたい」そう願うなら、資産形成は避けて通れない道でしょう。
しかし、投資と聞くと「難しそう」「損をしてしまうかも」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
そして、その結果、「やっぱり貯蓄が一番無難」と思って、思考停止してしまいがちです(過去の私がそうでした)。
資産形成は決して難しいものではありません。
大切なのは、リスクとリターンという2つの言葉を理解することです。
この2つの関係性をしっかりと把握することで、あなたに合った投資方法を見つけることができます。
このページでは、資産形成初心者の方でもできるだけわかりやすく、
リスクとリターン、とりわけリスクについて解説していきます。
資産を増やすための基本的な考え方
これまでの記事でも何度も記載しているため、しつこいかもしれませんが、
このブログでは本質や根底の考え方をできるだけお伝えしたいため、同じことを何度も記載することがあるのでご了承ください。
資産を増やすためには、大きく分けて3つの方法があります。改めておさらいをしていきましょう。
①収入を増やす: 仕事のスキルアップや副業などを通じて、収入を増やす方法。
②支出を減らす: 生活費を見直し、無駄な支出を削減することで、貯蓄を増やす方法です。
③投資をする: 生活防衛資金を除いた余剰のお金を投資に回すことで、お金に働いてもらう方法です。
今回のリスク・リターンの考え方は、「③投資をする」場合に押さえておかねばならないポイントとなります。
リスクとリターンとは?その関係性は?
リターンとは、投資によって得られる収益のことです。
具体的には、株式からの配当、株式の売却益、不動産賃料収入などが挙げられます。
一方で、リスクとは、投資によって損失が生じる可能性のことです。
具体的には、投資した金額が元本割れする可能性や、期待していた収益が得られない可能性などが挙げられます。
(※リスクという言葉は、経済学上の定義だと、ばらつきを指すものなのですが、複雑になるため、ここではイメージがしやすいリスクの定義を挙げております。)
リスクとリターンは表裏一体の関係にあります。
つまり、高いリターンを得ようと思えば、それだけ大きなリスクを伴うということです。
逆に、リスクを低く抑えようとすれば、得られるリターンも小さくなる傾向にあります。
これを「ハイリスク・ハイリターン」「ローリスク・ローリターン」と呼びます。
冒頭で、「やっぱり貯蓄が一番無難」と考えてしまうのは、投資におけるリスクを意識しすぎてしまい、
「ローリスク・ローリターン」の貯蓄を選択してしまうという行動ということになります。
その背景には、リスクに対する過剰な恐怖や誤解があることが大きいと考えています。
(日本はお金に対する教育をきちんとしないので、大損をした人の悪い情報か、爆益のような詐欺まがいの一攫千金情報ばかりが出回っていることも、過剰な恐怖や誤解を与えている要因だと思います。)
リスクの種類を徹底解説
投資においてどんなリスクの種類がある?
リスクについては、きちんとした理解をするべきなので詳細に記載いたします。
投資に関するリスクは6つほどに大別されます。
少し難しい表現もあるかと思いますが大事なのでぜひゆっくり読んでみてください。
- 市場リスク
市場リスクとは、株式市場や債券市場など、全体の市場が変動することによって生じるリスクです。
経済状況の変化、政治情勢の変化、自然災害など、様々な要因によって市場が大きく変動し、投資した資産の価格が下落する可能性があります。
例えば、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災、2020年のコロナショック等などが挙げられます。景気後退によって、多くの企業の業績が悪化し、株価が大幅に下落しましたよね。
- 信用リスク
信用リスクとは、債券を発行した企業や国が、債務を履行できなくなるリスクです。
企業が倒産したり、国がデフォルト(債務不履行)を起こしたりした場合、
投資した債券の価値が大幅に下落する可能性があります。
例えば、エチオピアは2023年にデフォルトしました。内戦やコロナショックの影響で経済が疲弊していたことが原因です。
- 流動性リスク
流動性リスクとは、投資した資産をすぐに現金化できないリスクです。
上場していない非上場株式や不動産などは、売却までに時間がかかったり、希望の価格で売却できない可能性があります。
例えば、不動産はイメージしやすいですね。売りたいと思ってもすぐに売れるわけではなく、タイムラグがどうしても生じます。
- 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利が変動することによって、投資した資産の価格が変動するリスクです。
特に、債券は金利と価格が逆の動きをするため、金利上昇時には債券価格が下落する可能性があります。
例えば、長期国債を保有している場合、金利上昇により、債券価格が下落します。
- 為替変動リスク
為替変動リスクとは、外国通貨建ての資産に投資している場合に、為替レートの変動によって生じるリスクです。例えば、円高になると、外国通貨建ての資産を円に換算した場合、円ベースで評価額が下落する可能性があります。
例えば、ドル建ての株式に投資している場合、円高になると、円ベースでの評価額が下落します。
- その他のリスク
カントリーリスク:
特定の国に投資する際に、その国の政治情勢や経済状況が悪化することで、投資損失が発生するリスク。
例えば、発展途上国は今後の成長という意味では魅力的ですが、国自体は不安定ですよね。
業種リスク:
特定の業種に特化した投資信託の場合、その業種特有のリスクにさらされるリスク。
例えば、2000年代初期のITバブル崩壊によってIT業界はマイナスダメージを受けました。
また2008年のリーマンショック時には、特に金融業界がダメージを受けましたよね。
2024年時点では、AIバブルがおきており、AIに関する業界の見通しが良くも悪くも目にします。
リスクに対する考え方・軽減方法とは?
前述したように、市場リスク、信用リスク、流動性リスクなど、投資には様々なリスクが存在しますが、
リスクだけ見ていると、不安が増して投資に対して躊躇してしまいますよね・・・。
では、これらのリスクをどのように軽減すれば良いのでしょうか。
以下の3つを押さえておくことで、リスクの多くは回避できます。
資産形成において、特に重要な考え方になるので是非押さえてください。
1. 分散投資
分散投資とは、一つの投資商品に集中して投資するのではなく、複数の資産クラス(株式、債券、不動産など)や、複数の銘柄に分散して投資する方法です。これにより、特定の資産の価格が下落した場合の影響を軽減することができます。
例えば2024年12月現在、日産自動車が業績が低迷しており株価が大暴落しています。日産自動車の株式だけを購入すると打撃をうけますが、トヨタ等も含まれる自動車業界全体に投資する投資信託であれば、リスクを軽減すること可能ですよね。
国も同様です。発展途上国・新興国だけに投資するよりも、アメリカや日本といった先進国も含めて、幅広い国に投資をしたほうがリスクは減るはずです。
※発展途上国・新興国だけに投資して、一攫千金を狙うような手法は当ブログでは推奨していません。
あくまできちんとした資産形成をするための考え方が大事です。
2. 長期投資
長期投資とは、短期的視点ではなく、長期的な視点で投資を行うことです。
短期的な市場の変動に一喜一憂せず、長期的に見れば、株式市場は上昇傾向にあるという歴史的な事実を踏まえて、じっくりと資産を増やしていく投資方法です。
先ほど、「1.市場リスク」で、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災、2020年のコロナショック等で株価が低迷したことを記載しましたが、その時点の株価と、2024年時点の株価で比較すると、2024年時点のほうが低いでしょうか。いえ、高いのです。
その時々の状況によって、株価は短期的には乱高下しますが、長期的に見れば右肩上がりとなります。
それは資本主義のメカニズムそのものであるからです。
今からスマホがなかった時代に戻れますでしょうか?また車がなかった馬の時代に戻れますでしょうか?
(資本主義については過去記事を参考にしてください。
経済の仕組みがわかる!資本主義ゲームで成功するための考え方)
人間は昨日よりも明日を豊かにしたいと思う生き物です。欲深いともいえます。
なので地球が崩壊しない限り(またはAIに人間が支配されない限り)、世界の成長や企業の成長が続き、株価は上がっていくという考え方になるわけです。
この「長期投資」をきちんと徹底できれば、先ほど挙げたリスクの多くは回避可能です。
(ただ、きちんと徹底するということが難しかったりします。どうしても短期的に株価が大暴落すると、不安になって売りたくなってしまうためです。投資に対するマインドについても別記事で触れたいと思います)
3. 定期積立投資
定期積立投資とは、毎日や毎月に一定額(例えば1000円とか1万円とか10万円とか)を投資信託などに自動的に積み立てていく投資方法です。
ドル・コスト平均法とも呼ばれ、市場の価格変動に左右されずに、計画的に投資を続けていくことで、購入単価の平均化を図り、投資のリスクを分散させる手法です。
同じ金額を淡々と積み立てることで、株価が高いときは少ない株数を買い、株価が低いときは多くの株を買うことができるため、購入単価の平均化につながるわけです。
例えば、毎月1万円を投資信託に投資したとします。
当初は順調に成長していますが(●と△)、突然リーマンショックを上回る大暴落が起きたとします(■と♢)。
暴落時に不安になって売らず、淡々と購入を続けていれば、平均株価は落ち着いてくるわけです。
●月●日:株価100円→100株購入(資金10,000円÷株価100円)
△月△日:株価200円→50株購入(資金10,000円÷株価200円)
■月■日:株価50円→200株購入(資金10,000円÷株価50円)
♢月♢日:株価80円→125株購入(資金10,000円÷株価80円)
→合計40,000円を投資 ÷ 475株購入=平均84.2円
この定期積立投資は、長期投資との親和性も高いわけです。
短期的な株価下落はコツコツ積み立てることでリスクヘッジし、
長期的には株価が右肩上がりになるため、その上がったタイミングで大きく利益を獲得することが可能です。
当記事ではリスク・リターンの定義をご紹介しつつ、特に皆さんが気になるリスクについて記載いたしました。
確かに投資にリスクは伴うものの、「分散投資」、「長期投資」、「積立投資」の3つを徹底していれば、リスクは一程度回避可能なものだと考えています。
この記事の考え方はすごく大事ですので、是非振り返ってみてもらえればと思います。
具体的に何に投資すべきか等はおいおい記事にしていきます。

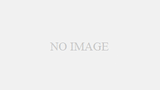
コメント